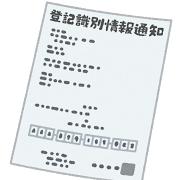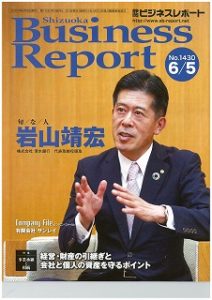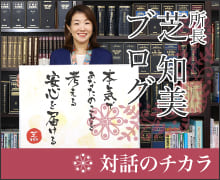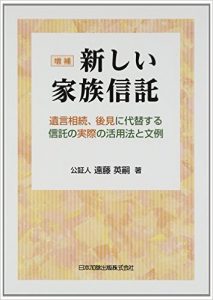
信託の分野で有名な著者遠藤先生の
勉強会に参加してきました
何かしらの障害を持った子供をお持ちの親は
自分が亡くなった後に、その子供の面倒を誰が
見てくれるのか不安に思う方も多い。
子供の兄弟や親戚等が面倒をみることが
多いとしても、親が亡くなった後は自分(親)が
監視するわけにはいかないのだし、
せっかく子供のためにと残した財産を
適切に使用してもらえるのか、不安が残る。
そんな場合に、財産を信託して
子供に残すという方法があります
委託者(多くは親)が受益者(子供)のため
信頼できる受託者(子供の兄弟や親戚等)に
財産を託し、管理処分をまかせて
将来にわたる子の面倒を託すもの
信託銀行の行う信託ではなく、
主に家族間で設定する信託のため、
家族信託と呼ばれています。
受託者が親族等であることに特徴があります。
私達司法書士や弁護士は業として行う場合には
信託業法の許可が必要になってしまうので
原則として受けられません。
信託契約により管理の仕方等を指定できるし、
受益者代理人や信託監督人等を設けることで
適切な運用ができているかどうか受託者を
監督することもできます
(受益者代理人、信託監督人には
司法書士もなれます )
)
また子供が死亡した後に、信託した財産を
どのように承継するかを信託契約に定めておくこと
も可能
画期的なことが多い信託ですが、
なかなか利用が進んでいないのは、
仕組みがややこしいということと、
もう一つ、信頼できる受託者がいないということ
このところ信託のご相談を受けるようになりましたが
受託者探しが難航しているケースが多いのです。
特に親が高齢で今後の不安から相談にいらっしゃる場合は、
お子さん(受益者)が40代、50代の場合が多く、
子供が亡くなるまでとなると、
親なきあと信託を設定した場合、
受託者は数十年仕事が続いていくことになります。
気軽には引き受けられませんよね
少子化の影響もあり、兄弟や親戚がいないという環境は
ますます増えていくでしょうから、
信頼できる受託者をどう確保するのか、
信託業法の見直しも含めて大きな課題です。
![job_teacher_woman[1]](https://www.shibajimusho.or.jp/wp-content/uploads/2016/07/job_teacher_woman1-230x300.png)
![]()
![]()
![]()
![]()



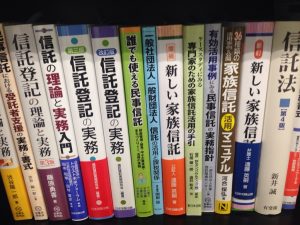
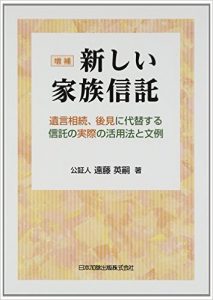


![soudan_kotowaru[1]](https://www.shibajimusho.or.jp/wp-content/uploads/2016/05/soudan_kotowaru1-300x291.png)