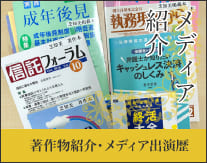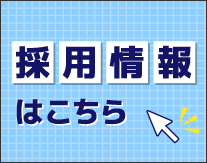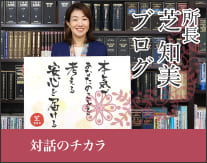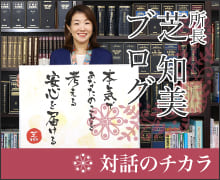Question
土地・建物の名義替えをしたいです。どうしたらいいですか。
Answer
誰に、どのような原因で名義を変えるのか、決めましょう。
登記を変更する前に必ず「税金」の確認をしましょう。
名義替えといっても、どのような原因で変更するかによって手続きが異なります。
名義を変えてもらう代わりに、お金を払う場合は「売買」
名義を変えてもらうが、お金は支払わない(もらう)場合には「贈与」
という原因になります。
登記は、当事者の意思が確認され、書類が揃えば、
いつでも変更することが可能です。
当事者同士が名義を変えることに同意していることを前提として、
名義を変える際に一番気を付けなくてはいけないのは税金の確認です。
「売買」の場合には、不動産取得税、不動産譲渡税が、
「贈与」の場合には、贈与税がかかります。
登記の名義を変更した後に、予想外の高額な税金を請求されては
大変です。
名義変更を行う前に、必ず税金の確認を行いましょう。
夫婦や親子等、家族内の名義変更の場合には
一定の要件に当てはまれば、税金の優遇措置もあります。
国税局HPhttp://www.nta.go.jp/index.htm