芝豊の1周忌に配布された本。
書籍になっていない論文等をまとめたものです。
非売品となっています。
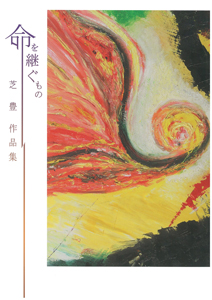


芝豊の1周忌に配布された本。
書籍になっていない論文等をまとめたものです。
非売品となっています。
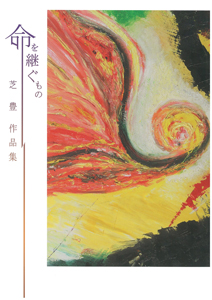


●登記(所有権移転) 30代 女性
【感想】
見積もりや必要書類等の連絡がすぐにいただけました。
依頼してからも無駄なくスムーズで、適切なアドバイスもしてくださり、安心してお願いできました。
【事務職員の対応】
事務所にうかがった時に、丁寧に対応していただきました。
緊張してしまうような場所なので、もう少し笑顔を見せていただければ気持ちがほぐれると思います。
【その他】
経験の無い素人でしたが、無事に済ますことができて感謝しています。

●相続 40代 女性
【感想】
複雑な相続問題をとても親身にかつていねいに処理してくださいまして、本当に有難く、不安でいっぱいの私共を気づかっていただき、いつも安心感を持たせて下さったことが、大変好印象を持ちました。
【事務職員の対応】
電話対応、書類送付等、親切でていねいなお仕事でした。連絡内容もよく理解できるようわかりやすく説明していただき、混乱せずにすみました。
【その他】
不安でいっぱいの私たちに、常に安心感が持てるよう、冷静に落ち着いた対応をしていただき、心の底から救われてよかった、助かったと感謝の気持ちでいっぱいです。
再生手続を行う事によって、滞納税金についても減額されますか。
滞納税金などの租税公課については、個人再生の手続きによっても
支払額の減額を受けることはできません。
租税公課は、民事再生法における一般優先債権とされています。
滞納税金がある場合には,滞納税金の支払いについても
考慮して再生計画を立てる必要があります。
参考条文(民事再生法)
第122条
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権
(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
自由財産として認められる財産は、どのようなものですか?
破産法第34条3項に定める以下の財産です。
① 99万円までの現金
② 差押禁止動産(民事執行法131条)
・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・一月間の生活に必要な食料及び燃料
・農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜
及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
・漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、
えさ及び稚魚その他これに類する水産物
・術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業
又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことが
できない器具その他の物など
③ 差押禁止債権(民事執行法152条)
・給料債権のうち、税金等を控除した額の4分の3に相当する部分
・退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分
など
破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか
一定の財産は、破産をしても破産者が保持することができます。
破産手続では、破産者が持っている財産を処分して債権者へ配当することが原則必要ですが、
全ての財産を処分してしまうと破産者が生活することができなくなってしまう可能性があります。
よって、個人破産の場合、破産開始前に所有していた財産のうち一定の財産はそのまま保持
することができ、これを自由財産といいます。
破産申立てをしたいのですが、どこの裁判所に申立をするのですか
A つぎの土地管轄により定められる地方裁判所に申立をします。(破産法第5条第1項)
①債務者が営業者であるとき
主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
②債務者が外国に主たる営業所を有するとき
日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
③債務者が営業者でないとき(個人の場合)
債務者の住所地
日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所
居所が知れない時は最後の住所地
補充的土地管轄
土地管轄によって管轄裁判所が定まらないときは、債務者の財産の所在地
(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所に申立をすることができます。
(破産法第5条第2項)
破産事件の管轄は、専属管轄であるので、当事者が合意によって管轄をさだめることはできません。
個人再生を申し立てることよって既に為されている給料の差押えを取り消すことができますか?
個人再生の申立をするだけでは、給料の差押えを完全に取り消すことはできません。
強制執行を中止した後(参照QA個人民事再生Q9)に、
強制執行の取消を申し立てる必要があります。
ただし、取消は給料の差押えを完全に取り消す手続きであるため、
取消が再生手続きにおいて必要と認められる場合であり、
担保が必要となる場合があります。
再生手計画が認可確定されれば、給料の差押えは失効します。
参考 民事再生法39条 2項
裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、
再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により
中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく
外国租税滞納処分の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、
再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、
又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続
又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
個人再生をする予定ですが、給料の差押えを受けています。給料の差押えを止める方法はありますか。
個人再生の申立と同時に強制執行中止命令申立をする方法があります。
しかし、給料の差押えを停止させるだけであり、差押えを受けた給料は
勤め先の会社に留保されることになり、債務者には支払われません。
また、再生手続きの開始決定があったときは、給料の差押えは中止されます。
いずれにしても、
速やかに再生申立をして、早期の開始決定を求めていくことが必要
になります。
参考条文(民事再生法)
第26条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、
再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続
又は処分の中止を命ずることができる。
二 再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は
再生債権を被担保債権とする留置権
(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)
による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく
強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して
既にされているもの
第39条
再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、
再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する
再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分
又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、
再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく
強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分
並びに再生債権に基づく財産開示手続は中止し、
特別清算手続はその効力を失う。
書籍を出版しました。
芝が司法書士ADRの部分を担当しています。
挨拶を交わせる関係へー司法書士ADRによる紛争解決とは
芝知美


日本評論社
9月10日発売
また下村隆先生執筆の
裁判事務に「技あり!」
ー民訴法上の特別代理人選任申立て体験記
の中に、芝事務所初代所長芝豊が登場します!
こちらも合わせてご覧ください。