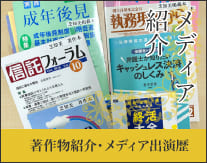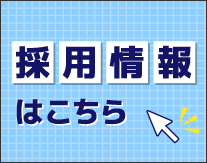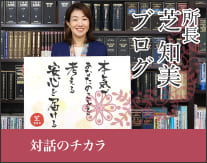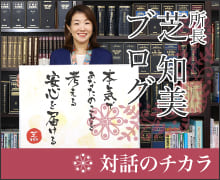![]()
自筆証書遺言を書きたいのですが、不動産や預貯金の細かい財産をすべて
手書きで書くのが大変です。
なにかいい方法はありますか?
![]()
平成31年1月13日施行の民法改正において、
自筆証書遺言の方式のうち、財産目録については自書する必要がないと改正されました。
財産目録については、例えばパソコン等により作成することもできますし、
不動産の登記事項証明書や、預貯金通帳のコピーを使用することもできます。
ただし、この方法による場合、遺言者は、自書以外で記載された全てのページに署名押印をする必要があります。
利用しやすくなったことにより、偽造変造の危険性が高まることのないよう、このような改正となりました。
なお、財産目録以外の部分については、以前と同じく自書が必要ですので、注意してください。
アーカイブ
-
-
【相続/Q38 】兄弟姉妹が相続人の場合、異父兄弟または異母兄弟も相続人に含まれるの?

兄弟姉妹が相続人の場合、異父兄弟または異母兄弟も相続人に含まれるのでしょうか?

兄弟姉妹には異父兄弟や異母兄弟も含みます。
ただし、異父母兄弟姉妹の相続分は、
両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。 -
【相続/Q37】遺産分割調停中の被相続人の債務の支払いは?

遺産分割協議でもめてしまい、調停中です。
亡くなった父が残した債務があり、返済を立て替えられないです。どうすればいいでしょうか?

遺産分割前の仮払いの手続きをしましょう。
令和1年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」において、
遺産分割前の仮払いを認める制度が新設されました。
家庭裁判所で遺産分割調停等を行っている最中であることが要件ですが、
家庭裁判所の審査を経れば、払戻し可能な金額に法定の制限がありません。
なお、仮払いが認められるのは、
「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により」必要があるとき
(家事事件手続法第200条第3項)とされており、必要性については家庭裁判所が判断します。
また、「他の相続人の利益を害するとき」には仮払いは認められませんが、
場合によっては法定相続分を超えた払戻しが認められることもあります。 -
【相続/Q36】相続財産の口座が凍結されてしまったら?

父が亡くなり、相続財産から葬儀費用を引き出そうとしたら口座が凍結されてしまいました。
引き出すには相続人全員の承認が必要ですか?

一定の金額までは、同意なく引き出すことができます。
以前は、早急な預貯金の引き出しが必要な場合でも、
原則相続人全員の同意が必要でしたが、令和1年7月1日に施行された
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」において、
遺産分割前の仮払いを認める制度が新設されました。
これにより、葬儀費用や必要生計費等、
早急に預貯金の払戻しを受けたいというニーズに
応えることができるようになりました。
払戻しには家庭裁判所の手続きは不要で、
相続人のうちの1人が単独で払戻しができるかわりに、
その額に制限を設けています。
その制限とは、新設された第909条の2に定めがあり、
① 相続開始時の預貯金債権×1/3×法定相続分
② 法務省令で定める額(150万円)
とされています。
なお、この限度額は金融機関ごとの上限であり、
他の金融機関にも口座があれば、そちらの預貯金についても
計算した上限額まで払戻しが可能です。 -
【相続/Q35】生涯独身の兄が亡くなったら、実家の土地や建物は私が相続するの?

私の兄は生涯独身で、子どももいません。
兄が亡くなったら、実家の土地や建物は私が相続するのでしょうか?

亡くなった方(被相続人)に、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
事実婚(いわゆる内縁)の配偶者は、相続人になりません。
法律に定められた相続人の順位は、以下のとおりです。
第1順位 子ども(離婚して親権のない子どもや認知した婚外子を含みます。)
第2順位 直系尊属(親や祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
この質問では、兄が配偶者も子どももなく亡くなった時に、
父母が生存していれば、相続人は父母になります。
しかし、兄の死亡時に父母もすでに亡くなっている場合、
兄弟姉妹が相続人となります。 -
【相続/Q34】相続人が誰もいない場合、亡くなった人の財産はどうなるの?

相続人が誰もいない場合、亡くなった人の財産はどうなるの?

亡くなった方の利害関係人等の申立てにより
家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は相続財産を管理しながら、清算する業務を行います。
負債のあるときは、財産を換価するなどして債権者に弁済し、
まだ余る財産のあるときは、特別の縁故のあるもの(内縁の妻など)に財産分与し、
最終的な残余財産は、国庫に帰属するのです。
もし財産を残したい相手がいるのであれば、生前に手続き(遺言書の作成など)
をしておくようにしましょう。 -
【相続/Q33】特別代理人は誰がなるの?

特別代理人は誰がなるの?

特別代理人選任申立時に候補者を推薦することができます。
候補者は、司法書士や弁護士等の専門職のほか
相続人ではない親族(未成年者の祖父母やおじおば等)でも構いません。
ただし、最終的に誰を特別代理人として選任するかは裁判官が決めます。
特別代理人は、原則として未成年者の法定相続分を確保する内容の
遺産分割協議をする必要があります。
(申立の際に、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。)
もし、特別代理人を選任せずに遺産分割を行った場合、
その遺産分割は無効となりますので、ご注意ください。
当事務所では、家庭裁判所に提出する書類の準備、作成のお手伝いをすることができます。
ご相談ください。 -
【相続/Q32】相続人に未成年の子がいるときは?

相続人に未成年の子がいるときはどうすればいいのでしょうか?

未成年者一般的な法律行為は親権者が未成年者の法定代理人として
未成年者の代わりに意思決定等をします。
相続手続きで未成年者とその親権者が遺産分割協議をする場合、
利益相反行為に該当するため、未成年について、遺産分割協議を
するための特別代理人選任を申立て、家庭裁判所で選任してもらいます。
相続人である親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人が
遺産分割協議をすることになります。 -
【相続/Q31】相続放棄とは?

相続放棄とはどういうことなのでしょうか?

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、
これが認められれば、亡くなった方の相続人から外れる
(最初から相続人ではなかったことになる)というものです。
「亡き父の不動産については、私はいらないから放棄する。借金も私は負わない。」と
相続人間で取り決めたことをもって「相続放棄をした」という方がいらっしゃいますが、
家庭裁判所で申立を行わないと法律的な意味での「相続放棄」は認められません。
相続人間で取り決めただけでは負債は免除されませんので注意が必要です。 -
【相続/Q30】相続放棄の手続はどうすればいい?

相続放棄の手続はどうすればいいでしょうか?

相続放棄の手続は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
亡くなった方(被相続人)と、相続放棄をしたい方との関係を示す
書類を提出する必要があります。
相続放棄の申述は、原則として自分が相続人であることを知った時から
3か月以内にしなければなりません。
この期間を過ぎないように注意が必要です。
当事務所では、相続放棄をお考えの方に、書類の準備等のお手伝いをすることができます。
お早目にご相談ください。