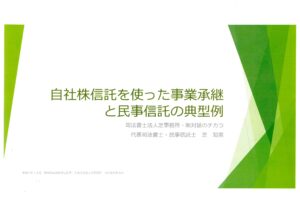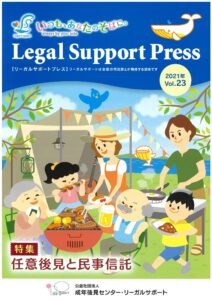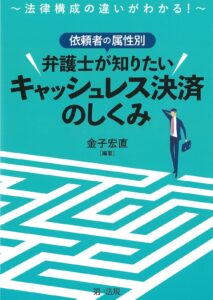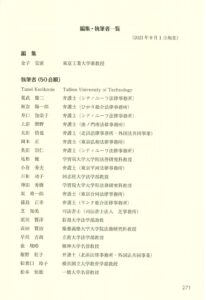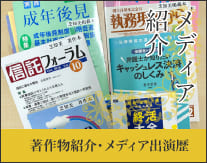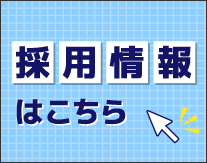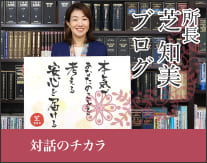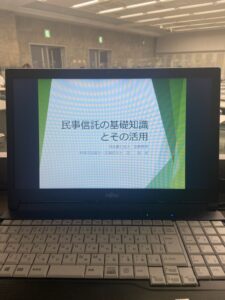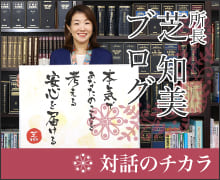こんにちは。大石です。
お昼、何食べてますか?
ちなみにある日のお昼ご飯のおかずはこちらでした。

※白米は別途持参
ナムルにコムタン風スープ。
無意識に、韓国風の組み合わせになってしまいました。
実は韓国料理はちょっとしたマイブームでして、
数年前に東京の新大久保でキムチやヤンニョムチキンなどを大量に食べすぎてついお腹を壊したことがあるほどに好きです(笑)
いつか本場に行って食べに行きたいですね。
そういえば、少し前にテレビで「辛い物を食べると脳内で幸せを感じる物質が分泌される」とやっていました。
辛いものが食べると舌が痛くなりますが、つい食べたくなるのは脳内物質のせいなのですね。
私のように食べ過ぎるのはNGですが、たまーにの楽しみに幸せを感じてみてはいかがでしょうか?
それではまた次回。