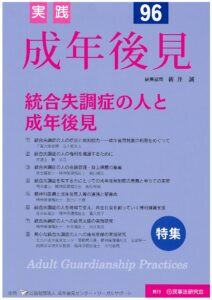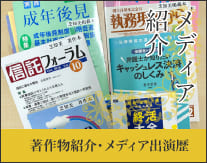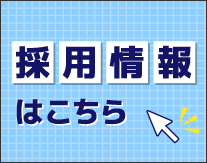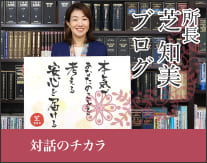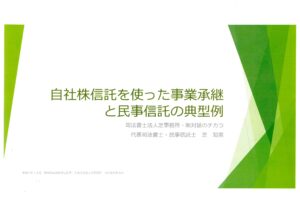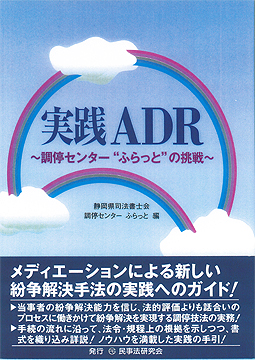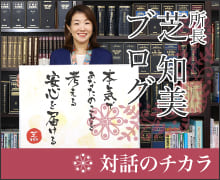Aさんは4社から500万円程の借金があり、自己破産を検討しています。
Aさんは携帯の利用料金を滞納しており、滞納金の中には端末代金の分割払い分も含まれています。
Aさんは自己破産によって携帯を解約されることはやむを得ないと思っていますが、自己破産後に改めて携帯の新規契約をすることはできるのでしょうか。
料金を滞納している場合、新規契約を拒否される可能性があります。
Aさんは利用料金が滞納状態のままでは、他の携帯会社に新規契約の申し込みをしても契約を拒否される可能性があります。
多くの携帯電話会社はTCA(電気通信事業者協会)という機関に加盟しており、契約解除後に料金を滞納している顧客の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申込時の加入審査に活用することにより、料金不払いの再発を防止するようにしています。
滞納料金を完済すれば滞納情報が消去されますが、支払不能になって以降又は破産手続開始の申立後に滞納料金を支払うことは、偏った弁済をしたことになるため、免責不許可事由に該当し、免責を受けられなくなる可能性があります。
免責許可決定確定後であれば携帯の新規契約は可能です。
不払い代金が完済されなければ、滞納情報は消えず、携帯の新規契約を結ぶことはできませんが、TCAの滞納情報は自己破産をして免責許可決定が確定した場合には抹消されることになっています。
免責許可決定確定後であれば携帯の新規契約は可能になります。
TCAの不払い情報の共有についてはこちらをご参照ください。
新規申し込みをするなら今までとは違う会社へ
どこの携帯電話会社もTCAの保有情報とは別に、自社の顧客データを保有しています。そのため、過去に利用料金を滞納して自己破産で免責されたという情報が残っている人が新規契約を申し込んでも断られる可能性があります。
自己破産後に携帯の新規契約の申し込みをする場合は、今までとは異なる携帯会社に申し込みすることをお勧めします。
司法書士 永野昌秀